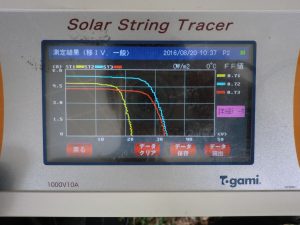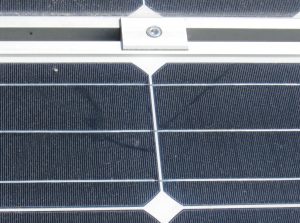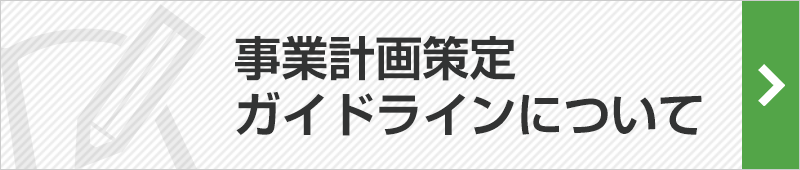テクノケアのメンテナンスとは
太陽光発電のメンテナンスとは
太陽光発電設備は、20年間メンテナンスをしなくても問題ない?
事業用の太陽光発電が本格的に普及し始めたのは、2012年7月からです。
それから約8年が経過し、設備の現場では様々な不具合が多発しています。
その現状を受け、2017年4月に改正FIT法が施行され、実質メンテナンスが義務化されました。
発電設備は、電気というなくてはならないインフラを支える事業です。
テクノケアでは、事業主様の資産を保持するという考えだけではなく
日本が保有している貴重なエネルギー資産と考え、
定期的な保守点検・メンテナンスを推奨しております。
★不具合に関する参考情報(別サイト)
太陽光発電チャンネル(資源エネルギー庁)
1:メンテナンス請負サービス
設備のメンテナンスを行います。
定期点検の場合は、下記①②までを基本サービスとしてご提案しております。
①各種機器による計測・測定
■ IVカーブ測定
住宅用からメガソーラーまで、各系統のストリング毎に専用測定器で計測。
ストリングの異常を発見します。
■ 絶縁抵抗測定
主に一次側(直流側)での計測を行い、基準値の合否にてご報告いたします。
ケーブルの劣化や、断線等の確認が可能です。
②架台・機器類の目視点検




点検表に基づき、設備全体から細部に至るまで目視点検を行います。
音・異臭・外観の確認から機器のエラーコード履歴のチェックまで、
幅広く点検。写真を添付し、わかりやすくご報告いたします。
③オプションサービス(別料金)
■ モジュールの低圧洗浄
表面についた汚れや異物を取り除き、ホットスポット等の不具合を防ぎます。
汚れがひどい場合は発電量の回復にもつながり、
過去には最大50%回復した事例もございます。
■ 雑草対策
- 定期的に刈払機で草刈りを行う
- 除草剤散布による定期除去
- 防草シートの敷設・修繕
をご提案させていただいております。
注意事項等もございますので、詳しくはお問い合わせください。
■ 不具合の特定調査
発電量低下の際の、不具合調査も実施しております。
また、以下のようなご相談が最近増えてきております。
- 毎月の売電金額が徐々に減ってきているので調べてほしい。
- 遠隔監視上で、エラーはないが特定のパワコンの発電量が昨年より落ちている。
- ブレーカが頻繁に落ちるため原因を調べてほしい。
最近非常に多い、シリコン系モジュールのクラスタ故障のモジュール特定調査も専用機器にて実施しております。
■ 各種交換・補修工事
これまで実施した設備に関連する主な工事・作業は以下の通りです。
- 盗難の際の幹線復旧工事
- モジュール交換工事パネル、パワコン、架台交換工事
(モジュールの寸法違いの工事も近年増えてきております) - パワコン交換工事(海外系のパワコンから高圧の集中型まで実施しております)
- 架台交換工事
- フェンス新設・補修工事
- メーター・VCT撤去工事
- 出力抑制設定変更
- 大規模修繕工事や、大規模修繕工事
■ 遠隔監視システム
当社独自の遠隔監視システムの設置提案を実施いたします。
パワコン1台につき1つのセンサーを設置することで、
パワコンごとの監視が可能です。
様々な状況に応じて自由にシステムの設置が可能です。ぜひご相談ください。
■ 緊急駆け付け対応
遠隔監視などで不具合が想定される場合、お客様や販売店に替わって
現地に駆けつけ、一次対応をとらせていただいた上でご報告いたします。
全国各エリアで対応が可能です。
■ 防犯カメラ
現場の地形に合わせて、防犯カメラの設置提案を行います。
盗難やイタズラだけではなく、積雪などの現場確認が可能です。
メンテナンスのコストを抑えることにもつながります。
■ キュービクル保守業務(高圧設備)
保守会社と提携し、高圧設備の保守業務を行います。
地域の保安協会より安価なご提供が可能です。全国各地で対応しております。
2:診断・セミナー・コンサルティングサービス
セミナー・コンサルティングサービス
現在JPMA((社)太陽光発電安全保安協会)が開催する
「太陽光発電メンテナンス技士」資格認定講座の指定講師や、
提携団体様のセミナー講師を行っております。
セミナー・研修を開催予定の方は、ぜひご相談ください。
改正FIT法への対応支援
メンテナンスをご検討頂いている方のご要望に応じて、
改正FIT法の解説書を差し上げております。
- 発電設備の標識および危険標識の作成と設置
太陽光発電看板・標識.comを運営しております。 - 費用年報の代行提出
こちらも行っております。お気軽にご相談ください。
テクノケアの強み
-
1.現場状況に応じて、様々なご提案が可能
設備の現場では、様々なことが起こっています。
雑草や獣害、天災や原因不明の不具合…。問題点は多様化しており、適切な対策を行うことが必要です。
当社では、現場状況に応じて様々な対策をご提案することが可能です。
-
2.他社にはない独自のサービスを全国で展開
フェンスの補修や周辺の木の伐採、架台の入替から設置などテクノケアならではのサービスも行っております。
お客様の要望を叶えることが私たちの仕事。
どんな内容でも、まずはご相談ください。
-
3.「太陽光発電メンテナンス技士」によるプロの技術
一般社団法人 太陽光発電安全保安協会の法人会員企業として、メンテナンスを熟知し、資格を所持しているプロが作業にあたっています。

■太陽光メンテナンス技士について(一般社団法人 太陽光発電安全保安協会)
太陽光発電メンテナンス技士 資格認定証
メンテナンスの基本的な知識
1:現場で起こりうる不具合
■ モジュール、架台周辺
■ パワコン・接続箱・集電箱
■ 設備全体
上記のような不具合が、多くの設備で起こっています。
緊急性は様々ですが、大きな事故や人命に関わるような事象を防ぐためにも
定期的なメンテナンスが必要になります。
2:どのようなメンテナンスを行うべきか?
必要なことは以下の3つです。
①ロスをいち早く発見する体制づくり
…定期点検の実施や頻度を増加、遠隔監視装置を導入し
タイムリーにロスを把握する
②将来の大きなロスに対する予防と対策
…定期点検時での対処、損害保険の加入等リスク対策
③発見時の迅速な対処
…施工会社との連携確認、対応サービスの検討
法律で安全・衛生のための教育が義務付けられているため、
テクノケアでは関係する各メンバーが以下の講習を受講済みです。
・低圧電気取扱業務特別教育
・高圧・特別高圧電気取扱者安全衛生特別教育講習会